こんにちは、わかるを助ける家庭教師の寺西です。
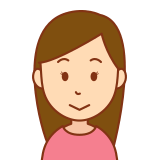
うちの子は優柔不断で、いつも自分で決められない…
将来、自分の意志で進路を選べるのかな?
そう不安に感じている保護者の方は多いのではないでしょうか。社会が複雑化する現代において、「自分で考え、決断し、行動する力」は、学力と同じくらい重要になってきています。
家庭教師として多くの親子を見てきた中で、「うちの子、自分で決められないんです」「考える力を付けさせたくて…」というご相談をよくいただきます。しかし、実際に親子の会話を聞いていると、親御さんの考えに誘導するような声かけになっているケースが多いのです。
親は本気で「この子のために」と、心配のあまり声かけをしているのですが、子どもにとっては「選択肢がない状態」に見えてしまうこともあります。
今回は、家庭教師として多くのお子さんと接してきた経験から、「自分で決断できる子」を育てるために親が意識すべき3つの接し方をお伝えします。
① 良い点と悪い点(メリットとデメリット)を伝える
「一人で考えなさい」と突き放してしまっても、情報や経験が少ないお子さんには、物事を判断する能力は大人ほどありません。そこで試していただきたいのが、メリット・デメリットを提示して、判断材料を与えてあげるという接し方です。
物事には良い点と悪い点、両方の側面があります。お子さんへの声かけの際には、「メリットとデメリットの両方を提示し、考えさせる」ことが重要です。
例えば、新しい習い事を検討しているとしましょう。
《親の気持ちが先行してしまうNGな声かけ》
「サッカーは運動になるから絶対にやった方がいいよ!頭も良くなるらしいし、絶対楽しいよ。」 →(親が決めているため、子どもは「やらされる」と感じてしまいます。)
《子どもの判断力を育むOKな声かけ(決断の材料を与えている)》
「サッカーをすると、体を思い切り動かせて、友達もたくさんできるという良い点(メリット)があるね。ただ、土日の朝が早くなくなることや、月々のお金がかかるという悪い点(デメリット)もあるよ。どうする?」
このように、親が一方的に「これがいい」と勧めるのではなく、決断の材料(情報)をすべて与え、比較検討させてみましょう。そうする事で、
- メリットとデメリットを正確に理解する力。
- どちらの要素(メリットとデメリット)を重視するかを考える力。
- 自分で情報を吟味して選んだという納得感。
を得ることに繋がります。
親は、ただ答えを与える人ではなく、「多角的な情報を提供するナビゲーター」に徹しましょう。
② 決めたことの理由を問いかける
決断力とは、「選ぶ行為そのもの」だけでなく、「選んだ理由を言語化する力」も含まれます。子どもが自分で決断したときこそ、親が踏み込んで話を聞くチャンスです。
《NGな声かけ(結果だけで判断)》
「それがいいなら、別にいいよ。」 →(子どもの思考プロセスに興味がないと伝わってしまいます。)
《子どもの判断軸を育むOKな声かけ》
「なるほど、A案を選んだんだね。〇〇(メリット・デメリット)があった中で、どうしてそっちにしたのか、ママ(パパ)に教えてくれる?」
この質問をすることで、子どもは「選んだ理由」を頭の中で再構築し、言葉にする訓練をします。
- 「だって、友達の○○ちゃんがやっているから」
- 「こっちの方が大変そうだけど、将来役に立ちそうだから」
どんな理由であれ、それを否定せず受け止め、「そうか、○○を大事にしているんだね」と共感することが重要です。この繰り返しで、「自分は何を基準に選ぶのか」という判断軸(自分軸)が、明確に育まれていきます。
③ 失敗しても「やり直すチャンス」を与える
決断力と切っても切れない関係にあるのが、「失敗への恐れ」です。親が完璧な決断を求めすぎると、子どもは「間違えたくないから、親に決めてほしい」と考えるようになります。
《NGな接し方(失敗を責める)》
「だからママ(パパ)が言った通りにしなさいって言ったでしょ!時間の無駄だったね。」
《決断への勇気を育むOKな接し方》
「失敗しちゃったね。でも、自分で決めて挑戦したことは素晴らしいよ。じゃあ、次うまくやるには、どうしたらいいと思う?」
自分で決めた結果、たとえ失敗したり後悔したりしても、それは「自分で責任を取る」という学びの貴重な機会です。親は、失敗した結果を責めるのではなく、「その失敗から何を学んだか」を一緒に考える伴走者になりましょう。
また、「たとえ失敗だらけの自分でも愛してもらえる」という、親の愛情に対する絶大な信頼感は、お子さんの自己肯定感をも育むことに繋がり、「失敗を恐れずにとりあえず挑戦してみよう!」という気持ちの土台にもなるのです。
「いつでもやり直せる」という安心感こそが、子どもに次の決断をする勇気を与え、決断力を確かなものに育てていきます。
親の「心配」を「信頼」に変える
お子さんの将来を案じる親御さんの気持ちは痛いほど分かります。しかし、その「心配」から来る先回りや誘導が、結果的にお子さんの決断する機会を奪っているかもしれません。
「自分で決断できる子」に育てるには、親が提供した情報をもとに、子ども自身が考え、選び、その結果を経験する小さな機会の積み重ねが必要です。
親の接し方を「心配」から「信頼」に変えて、今日から日常の小さな決断をお子さんに任せてみませんか。
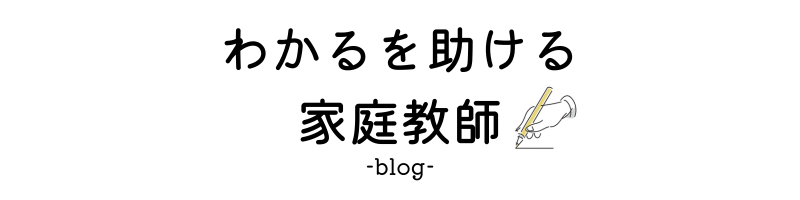
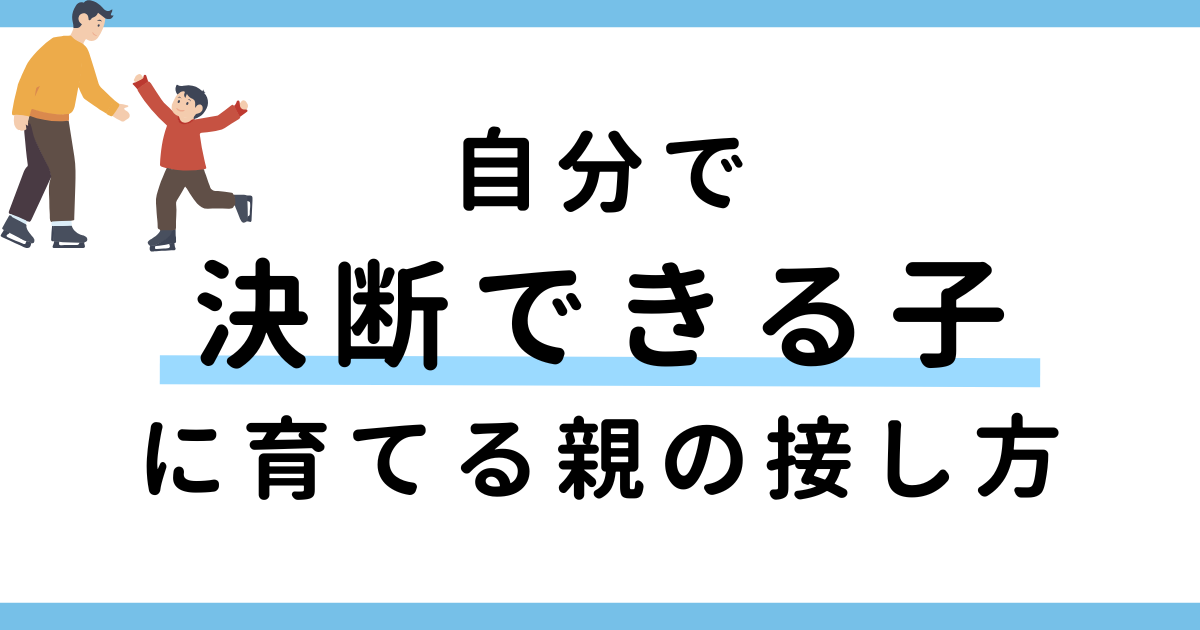
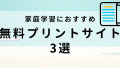
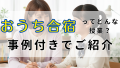
コメント