こんにちは、わかるを助ける家庭教師の寺西です。
今回は、とてもオーソドックスに「勉強のやり方」についてお伝えしようと思います。
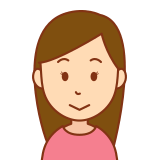
うちの子、机には向かっているのに、テストの点が伸びなくて…
やる気はあるのに、勉強の仕方が分からないみたい…
こうしたお悩みをお持ちのお子さまや、その保護者さまにぜひ読んでいただきたい内容です。
この記事を読むことで、「成績が上がる勉強法」のヒントがきっと見つかります。
「分かる」と「出来る」はちがう
成績を上げるために、まず知っておきたいのは「分かる」と「出来る」のちがいです。
- 「分かる」 … 内容を理解して「なるほど」と納得できる状態
- 「出来る」 … 理解したことを使って、実際に問題を解ける状態
勉強しているのに点数が上がらない子の多くは、「分かる」で止まってしまっています。
授業中は「分かった気がする」けれど、テストでは解けない…。
これは「分かる」勉強ばかりで、「出来る」勉強が足りない証拠です。
「分かる」ようになるための勉強=インプット
「分かる」ようになるための勉強とは、インプット中心です。
例えば、
- 学校や塾、映像などで授業を受ける
- 教科書(参考書)を読む
- ノートにまとめる
- 漢字や英単語を繰り返し書く
などです。
もちろん大切な作業ですが、これだけでは「知識をしまい込む」だけで終わってしまいます。
テスト本番で必要なのは「知識を引き出す力」なので、インプットだけでは不十分です。
「出来る」ようになるための勉強=アウトプット
「出来る」ようになるための勉強とは、アウトプット中心です。
例えば、
- 問題集を解く
- 小テストや模擬テストで確認をする
- 単語帳を使い、赤シートで隠しながら語句を思い出す
要するに「頭から情報を引っ張り出す練習」です。テスト本番では、先生が「答えを教えてくれる」ことはありません。
必要な知識を、自分の力で瞬時に呼び出せるかどうかが勝負になります。
インプット3:アウトプット7
では、インプットとアウトプットの理想的なバランスはどれくらいでしょうか?
答えは 3:7。
これは精神科医・樺沢紫苑先生の『アウトプット大全』にも書かれている黄金比率です。
私自身、数年前に「宅建士」の資格を取ったときも、この比率を意識して勉強しました。
テキストをざっと読んだら、すぐに過去問を解く。
3周解いても間違える問題は、4周・5周と繰り返す。
結局、知識は「何度も引き出して初めて定着する」のです。
人間の記憶は思った以上に弱いもの。
アウトプットを重ねなければ、せっかくの努力が水の泡になってしまいます。
モデルケース:数学の勉強
たとえば数学。
- インプット:解説を読んで「なるほど」と理解する。
- アウトプット:自分の手で問題を解いてみる。
この2ステップを必ずセットでやることが大切です。
学校で配られるワークは問題数が多いので、アウトプットするのに良い教材です。
また、手軽にアウトプットしたいなら、例えば受験研究社の『10分間復習ドリルシリーズ』のような、スキマ時間でも取り組めそうなドリルを使うのも良いでしょう。https://www.zoshindo.co.jp/junior/392/
「分かる」だけで終わっている子は、教科書を読んだり授業を聞いたりして安心してしまいます。
でも、それはまだ“練習試合前の作戦会議”の段階。
実際に戦えるようになるには、問題を解いて経験を積むしかありません。
だからこそ、私の授業では解説後に必ず問題を解かせますし、ご案内している市販教材はそのほとんどが問題集です。
まとめ
- 成績を上げるには「分かる」だけでなく「出来る」も大事
- インプット(分かる勉強)は全体の3割で十分
- アウトプット(出来る勉強)を7割にして、知識を引き出す練習を繰り返す
勉強しているのに結果が出ない…という方は、まずこの比率を意識してみてください。
きっと少しずつ、テストの点や成果が変わっていきます。
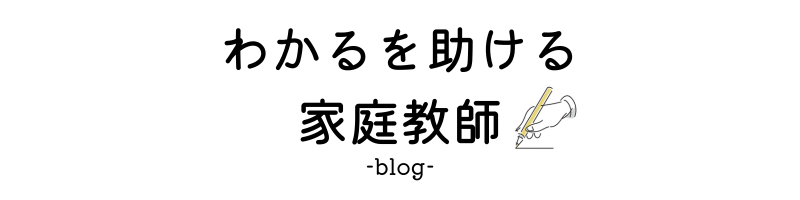
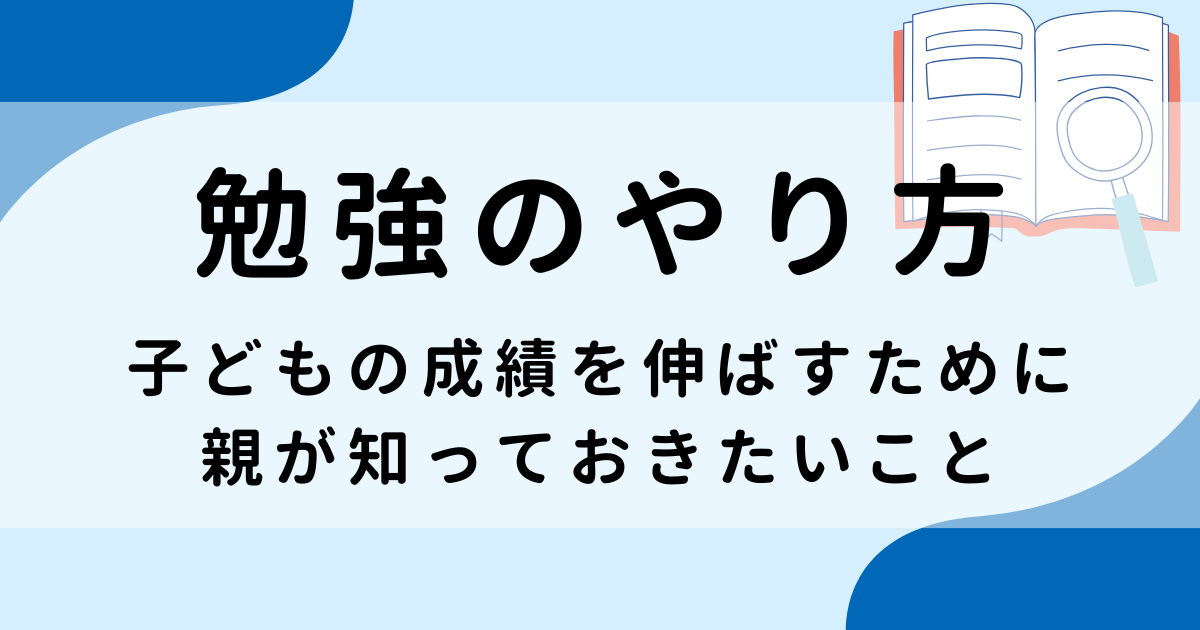
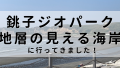
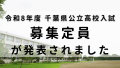
コメント